個人再生の最低弁済額|いくら減額される?
民事再生法では、「個人再生をしても、最低でもこれだけの借金は返済しなければならない」という最低弁済額が定められていま…[続きを読む]
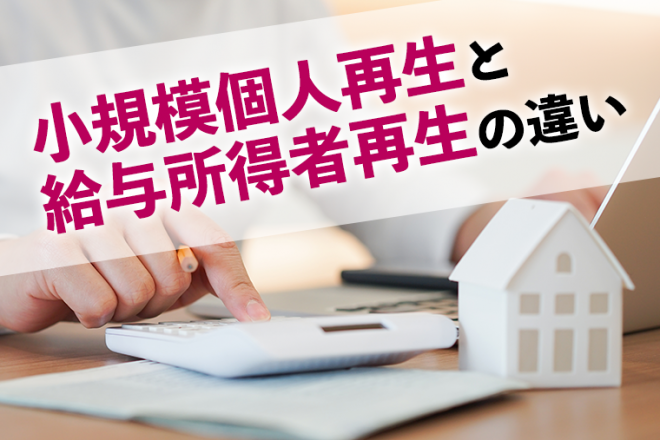
今抱えている借金の返済が困難な状況になった方の中には、個人再生を利用しようかとお悩みの方がいると思います。
個人再生とは、裁判所に申立てをして借金等の債務を大幅に減額したうえで、残債務を3年~5年かけて分割払いすることを可能にする手続です。
個人再生をするには、「継続的かつ反復した収入があること」という条件がありますが、これは個人再生後に減額した残債務を支払い続けるために必要な条件です。
そして、個人再生後に最低限いくら支払わなければならないか(=減額率)は、個人再生手続きの種類によって異なります。
これが、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」と呼ばれる個人再生手続きの違いです。
このうち、小規模個人再生の方が一般的な手続きで、小規模個人再生が難しい場合に給与所得等再生を選択することになるケースが多いです(どちらを選択するかは債務者が選ぶことができます)。
この記事では、小規模個人再生とはどのような手続きなのか?給与所得等再生との違いは何なのか?について説明します。
目次
個人再生手続きを利用する場合、基本的には小規模個人再生を利用することになります。そのため、まずは小規模個人再生の基本事項について説明します。
小規模個人再生とは、主に個人事業主を対象とした手続きとして制定されましたが、会社員や公務員などでも問題なく利用することができます。個人再生制度の一般的な手続きで、実際にほとんどの方は小規模個人再生を選択しています。
小規模個人再生の利用には、再生手続きで作成する「再生計画案」に対して、債権者の同意(債権者の頭数の半数以上の同意、又は債権総額の過半数を有する債権者の同意)が必要です。
この同意を得られない場合には、給与所得者等再生を選択することになるでしょう。
個人再生では、法律により、小規模個人再生・給与所得者等再生問わず手続き後に返済すべき最低金額(最低弁済額)が負債総額に対する割合で決められています。この最低返済額のことを「最低弁済基準額」といいます。
| 負債総額 | 最低返済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 負債総額すべて(減額なし) |
| 100万円超500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 負債総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 負債総額の10分の1 |
※上記の負債総額は、住宅ローンを除きます。
100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要があるため個人再生をする意味がありませんが、3,000万円を超えるほど高額な借金ならばその負債総額の10分の1が最低返済額となります。
つまり、住宅ローンを除いた債務額が3,000万円なら、最低返済額は300万円となるのです。
しかし、常に最低弁済基準額が個人再生後に返済すべき額になるわけではありません。
小規模個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」を比べて、高い方が返済すべき金額となります。
清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。
自己破産では、借金を原則として全額免除する代わりに、破産者が持っている価値ある資産(不動産、高価な車やブランド品、一定額以上の現金や預貯金など)が処分され、債権者に配当されます。よって、生活必需品等を除いた資産が多くある場合、小規模個人再生をすると最低弁済額が跳ね上がる可能性があります。
例えば、最低弁済基準額は300万円であっても、清算価値の合計が500万円であれば、個人再生後に弁済すべき額は500万円となります。
給与所得者等再生は、会社員など収入が安定しており、さらに将来の収入についても一定以上あると想定される債務者が利用できる手続きです。小規模個人再生よりも収入面の条件が厳しくなっているとお考えください。
小規模個人再生と異なり、再生計画に対して債権者からの反対等を受けても、再生計画に対する認可を得ることができます。
つまり、小規模個人再生で債権者から同意を得られなかった場合に、給与所得者等再生を選択するケースが多くなります。
なお、以下のことが過去7年以内にある場合は、給与所得者再生が利用できません。
給与所得者等再生では、最低弁済基準額・清算価値に加えて、可処分所得額の2年分も含めて比較をして一番高い金額を返済金額としなければなりません。
可処分所得は、次の式で求めます。
可処分所得 = 収入 -(社会保険料+所得税・住民税などの公租公課)- 最低生活費
つまり「可処分」とは、毎月の給与のうち税金や生活費を差し引いた、給与所得者が自由に使用できる所得のことです。
可処分所得額の2年分が最も高い金額となる事が多いとされます。よって、給与所得者再生は、小規模個人再生よりも返済額が高くなりがちです。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、両方とも「継続的に反復して収入を得る見込み」があることが要件となります。
しかし、給与所得者等再生は、加えて「給与など定期的収入で、変動幅が小さい(収入が安定している)」ことも要件となります。弁済すべき額も、給与所得者等再生の場合は「可処分所得の2年分の合計額以上」という点が加えられています。
また、先述のように、小規模個人再生・給与所得者等再生を問わず、再生手続きでは「再生計画案」を作成しますが、この計画案に対して、小規模個人再生の場合の債権者は反対する機会を得ることができます。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
|---|---|---|
| 共通要件 | 継続的に反復して収入を得る見込みがある | 継続的に反復して定期的な収入を得る見込みがある 収入の変動幅が少なく安定している |
| 弁済金額 | 最低弁済基準額と清算価値を比べて高い額 | 最低弁済基準額・清算価値・可処分所得の2年分の中で最も高い額 |
| 議決要件 | 債権者総数の半数以上かつ 債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対されない |
債権者からの異議があっても、裁判所が許可すれば手続可能 |
小規模個人再生では債権者に一定の同意(債権者数の過半数・債権額で1/2以上の消極的同意)を得る必要があるものの、給与所得者等再生より弁済すべき額が少なくなりますので、基本的には小規模個人再生を優先的に検討することになります。
他方、債権者の反対が多く小規模個人再生が利用できない場合には、給与所得者等再生を申し立てることになります。
なお、小規模個人再生あるいは給与所得者等再生で、期間や費用に大きな違いはありません。期間・費用に違いが出るのは、主に個人再生委員の専任の有無によるでしょう。
また、どちらの個人再生手続きでも官報への掲載は免れません。
具体的な個人再生手続きの流れについては、以下のコラムをご覧ください。
小規模個人再生の方が一般的とはいえ、いざ自分が個人再生を利用しようと考えた場合、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」どちらの手続きを選択するべきなのか?自分にとってメリットが大きい手続きはどちらなのか?と迷う方もいるかもしれません。
しかし実際には、債務者それぞれの様々な要素や希望を加味して、債務整理に強い弁護士・司法書士がどちらの手続きにするべきかを検討をしてくれますので、ご安心ください。
それ以外でも、個人再生では弁護士などの専門家に依頼して書類の提出を間違いなく行うことが重要です。
自力で申立てをしようとしても、書類などの不備により失敗してやり直しになってしまう可能性が高いでしょう。
あなたの状況にぴったりの借金解決方法を検討するならば、一度債務整理に強い弁護士・司法書士に相談してみることをお勧めします。