消滅時効援用通知書の書き方・書式・ テンプレートは?わかりやすく解説!
ここでは、時効を援用する際に必要な「消滅時効援用通知書」の書き方と、時効の援用の失敗を避けるためのポイントなどについ…[続きを読む]
「時効」という言葉自体は周知されています。
刑事ドラマなどでよく耳にする「時効」の概念から、「犯罪から逃げ切る(捜査を打ち切られる)」というようなイメージを持っていらっしゃる方も多いでしょう(公訴時効)。
実は、借金にも、「借金の時効」の概念が存在します。この記事では、借金の時効(消滅時効)について解説していきます。
目次
消滅時効とは、一定期間借金の返済を請求されなかった場合には、借金の返済義務を免除するという制度をいいます。
このように聞くと、借金を返せなくなった人の中には「時効で踏み倒せるのでは」などと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自力で対処しようとすると、時効の主張ができなくなってしまう(時効が更新して0から数え直しになる)ことがありますので、注意が必要です。
時効が成立している借金がある場合は、「援用」を専門家に依頼することで、時効の手続きを迅速に行ってくれます。
消滅時効の援用とは、時効の利益を受けると債務者が債権者に主張をすることを指します。
消滅時効による債務の消滅を主張するためには、消滅時効期間が経過したことのほかに、消滅時効を援用することが必要となります。
消滅時効が完成したとしても、任意に債務を支払いたいという人もいます。
このような人の意思を尊重するため、消滅時効による債務の消滅を認定するためには、「消滅時効が完成した」ことを主張することが必要とされています。
これを消滅時効の「援用」といいます。
弁護士などに依頼をして、「消滅時効の起算点などから見て、消滅時効期間が経過しているか」「時効の完成猶予事由(停止事由)や更新事由(中断事由)が発生していないか」を確認した上で、消滅時効が完成していることがわかれば、「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便の形式で作成します。
この消滅時効援用通知書を金融機関に郵送して、金融機関に到達すれば、消滅時効の援用は完了です。
なお、「起算点を間違えていた」などの理由で万が一時効の援用に失敗してしまったら、時効が完成していた債務を支払わなければならなくなる危険もあるので、時効援用は専門家に依頼して行ってもらうことをお勧めします。
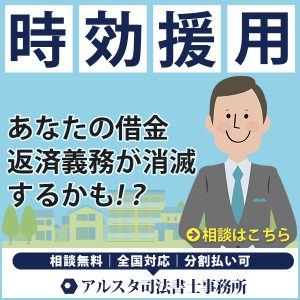
基本的に債権(借金)の消滅時効は、消滅時効期間が経過することによって成立します。
では、どれくらいの年数が経過すれば借金の消滅時効が完成するのでしょうか。
2020年4月1日に施行された新民法により消滅時効に関するルールが変更された関係で、借金の成立時期によって消滅時効期間が異なります。
それぞれのパターンについて詳しく解説します。
新民法施行前の2020年3月31日以前に成立した借金については、①通常の消滅時効が適用されるパターンと、②商事消滅時効が適用されるパターンの2つに分かれます。
友人や親、親戚などの個人から借金をした場合、「債権を行使できる時から10年」を経過すると、消滅時効が完成します。
なお、「行使できる時」とは、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)を意味します。
一方、銀行・信用金庫・信販会社・消費者金融など、会社に対する借金の場合には、より短い商事消滅時効が適用され、「債権を行使することができる時から5年」を経過すると消滅時効が完成します。
会社は営利上の目的により貸付けを行っていることから、債権を長く放置することは考えにくいという考慮が働き、改正前の民法では、通常よりも短い商事消滅時効が定められていました。
新民法が施行された2020年4月1日以降に成立した借金については、新民法の消滅時効に関するルールが適用されます。
新民法では、個人・会社の区別なく、すべての借金について以下の条件にて消滅時効が完成します。
①債権を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
②債権を行使することができる時(客観的起算点)から10年
上記①または②のうち、いずれか早く到来した時点をもって、借金の消滅時効が完成することになります。
とはいえ、①=②となることがほとんどのため、消滅時効は実質的に全て5年に短縮されたと考えて良いでしょう。
現段階で時効が問題となる借金は、原則①のケース(2020年3月31日以前に成立した借金)となるでしょう。
実は、仮に上記の消滅時効期間が経過していても、時効が成立しないケースがあります。
債権者がある一定の手続きを踏んだり、債務者が知らないうちに下記のような行為をしてしまったりすると、消滅時効は成立しません。
消滅時効は、一定の事由が発生した時点で中断(更新)され、またゼロからカウントし直しになってしまいます。
新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由としては、以下のとおりです。
- 裁判上の請求
- 差押え、仮差押えまたは仮処分
- 債務の承認
裁判上の請求とは、例えば、債権者が債務者に対して訴訟を提起したり、支払督促などを送付したりすると、時効期間は中断されます(しかし、訴えの却下又は取下げがあった場合には中断の効力を生じないとされています)。
また、債務の承認とは、債務者自身が借金の存在を明示的または黙示的に認めることをいいます。
債務の承認に該当する例としては、以下のようなものが挙げられます。
このように、債務の承認は債務者がうっかりやってしまいそうなことが多いですので、債権者は「分割払いでもいいですよ」「少しでも返済してくれれば利息をまけますよ」などと言い、時効の成立を防ごうとしてくることがあります。
一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の更新事由は以下のとおりです。
(「中断」から「更新」へと文言が改められていますが、時効のカウントが数え直しになるという意味では変わりがありません。)
時効の完成猶予事由(改正前民法では停止事由)が発生している間は、消滅時効期間が経過したとしても、消滅時効は完成しません。一時的に進行がストップし、その後、停止した期間からカウントが再スタートすることになります。
時効の完成猶予または停止に関するルールも、借金の成立時期が新民法施行より前か後かによって適用関係が異なります。
新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の停止事由は、以下のものが挙げられます。
例えば、自然災害により裁判所の業務が止まってしまうと、債権者は裁判上の請求のための申立てなどができなくなります。
この期間については、時効の進行が一時的に(その障害が消滅した時から2週間まで)ストップします。
内容証明郵便などによる裁判外での催告については、送った時点で一時的に時効が停止します。
つまり、時効期間が満了する直前に履行の催告をすることで時効を停止させ、債権者はその間(6ヶ月以内)に裁判上の請求をして時効の中断を狙ってくることがあるのです。
一方、新民法施行後の2020年4月1日以降に成立した借金の時効の完成猶予事由は以下のとおりです。
借金をしたけど返せないまま何年も過ぎている……という場合、その借金は時効(消滅時効)になっている可能性があります。借金の時効と成立の条件に付いてお話しします
今回は、借金の消滅時効について解説しました。
借金について消滅時効が完成しそうという場合には、借金の負担から解放されるために消滅時効の援用を検討しましょう。
しかし、実際には債権者が消滅時効の完成を放置する可能性は低く、特に金融機関などから借り入れを行っている場合には、消滅時効が完成することはほとんど期待できません。
その場合には、債務整理で借金の負担を軽減する方が現実的な選択肢となるでしょう。
消滅時効の援用や債務整理については、弁護士・司法書士・行政書士に相談することがおすすめです。
依頼者の債務の状況を十分に調査した上で「消滅時効を援用できるのか」「債務整理をすべきなのか」「どの債務整理手続きを利用すべきなのか」などを考慮し、依頼者にとって最適な解決方法を提案してくれます。
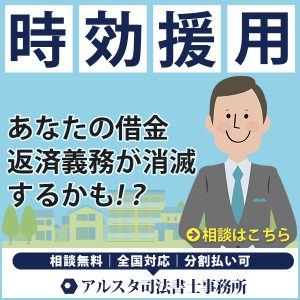
借金問題でお悩みの際には、一人で悩まずにお早めに専門家までご相談ください。